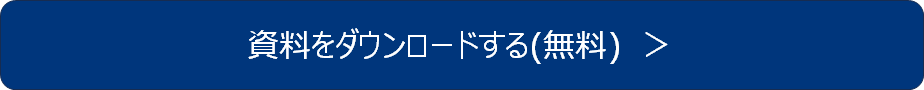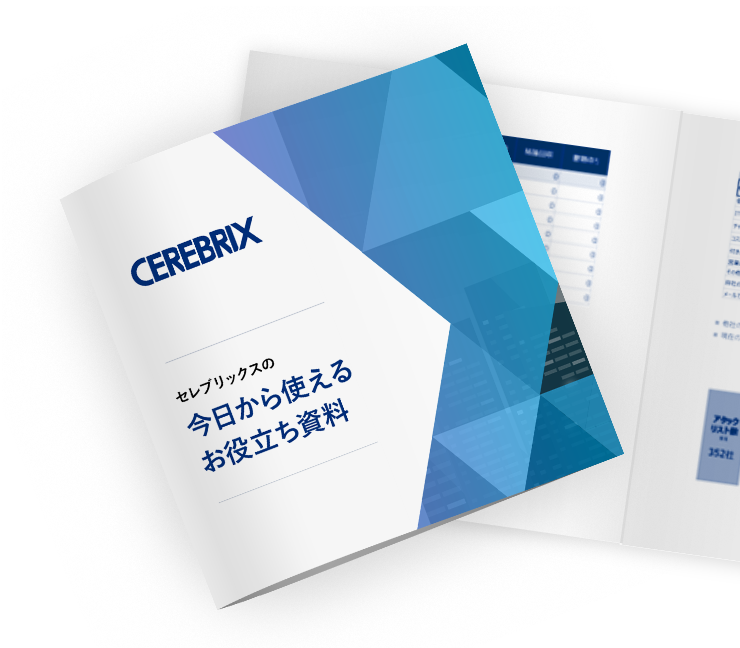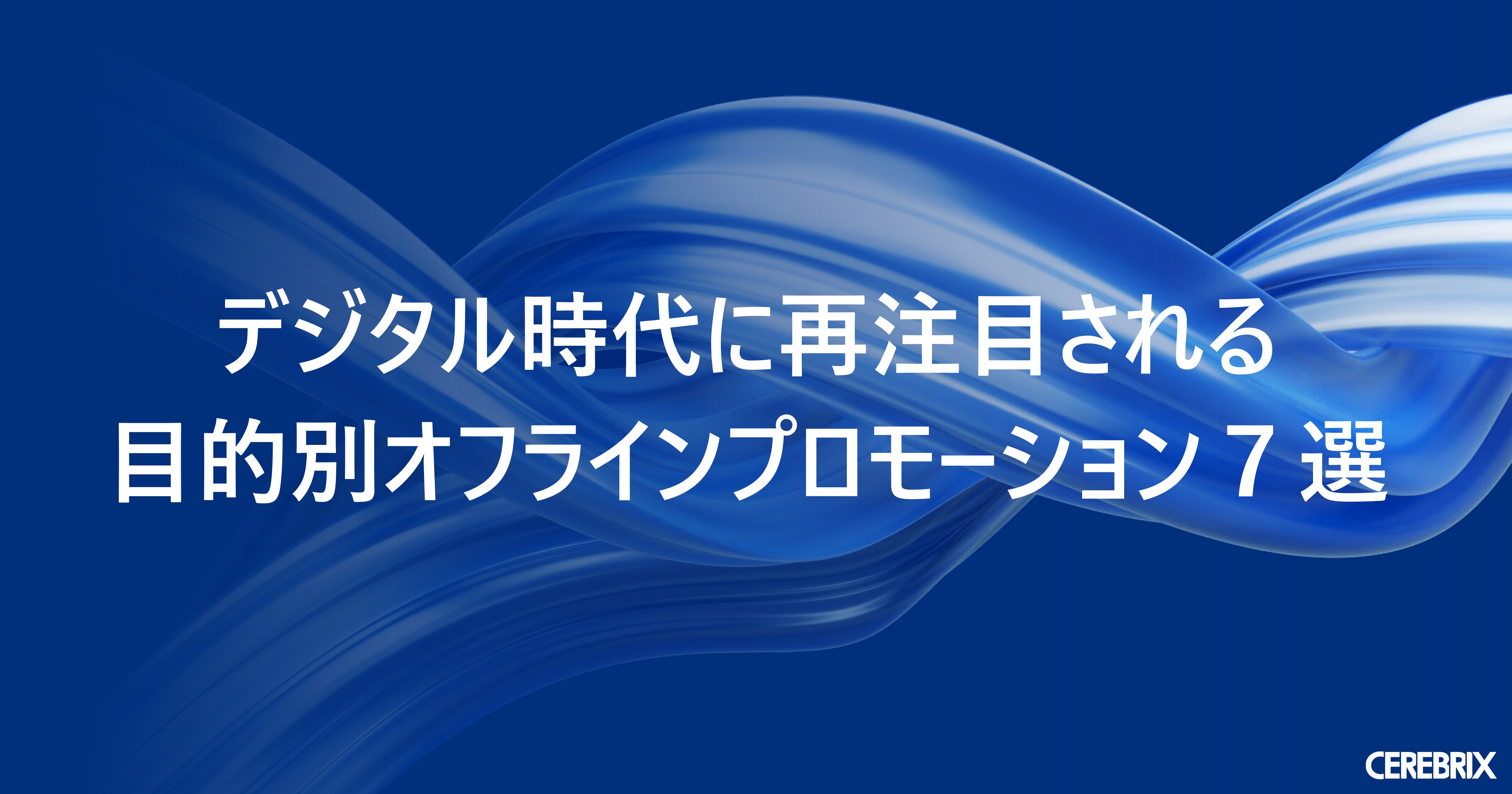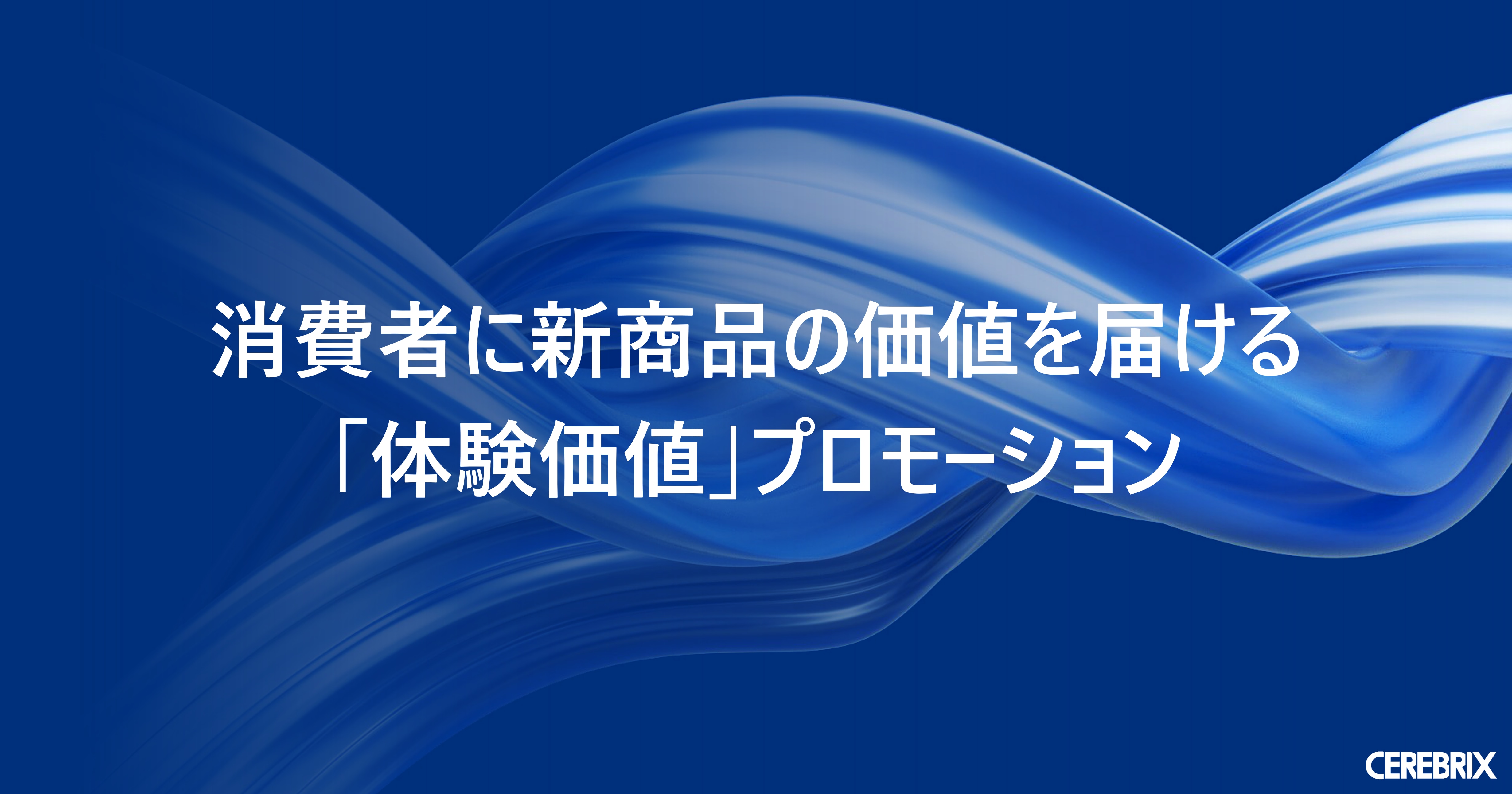若者を動かす食材宅配の会員獲得戦略
近年、食材宅配サービスは忙しい現代人の食生活を支える便利な仕組みとして、幅広い層に受け入れられつつあります。とはいえ、まだまだ「子育て世代や高齢者向け」という印象が根強く残っていることも事実です。
若い世代のなかにも「いざ自炊したいけれど、買い物や準備が大変…」「外食やテイクアウトに依存しすぎるのは避けたい」という声が増えています。そこには、食材宅配サービスを利用する大きな潜在ニーズが眠っていると言えるでしょう。
しかし、いざ若者を取り込もうとすると「競合サービスとの差別化が難しい」「そもそも食材宅配の仕組みが複雑そうに思われる」「コストや継続性に不安がある」といった課題に直面しやすいのではないでしょうか。
こうした障壁を乗り越えるには、オンラインの広告やSNS展開だけでは不十分です。むしろ、若者の物理的な「体験」を重視したオフラインプロモーションが決め手となり得ます。
そこで本記事では、食材宅配サービスにおける若者層の新規会員獲得という視点から、「フェス」など大規模イベントを含むオフラインの試食会や体験施策を活用する具体的な方法を提示します。
味のおいしさや、注文方法・システムが思ったより簡単であることを直感的に理解してもらうには、やはり人を介したリアルな接点が欠かせません。自社サービスへの若者流入を一気に加速させるヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
あわせてお読みください
本記事とあわせて、『デジタル時代に再注目される目的別オフラインプロモーション7選 』もぜひご活用ください。デジタルだけでは得られない【人を介したリアルな顧客体験】を提供するオフラインプロモーションの魅力に再注目。対面でコミュニケーションを図ることで、顧客の態度変容を促す手法をご紹介しています。
目次[非表示]
若者層を開拓する意義とは
食材宅配サービスの利用者といえば、従来は子育て世代や高齢者がメインでした。育児や体力面で買い物に行くのが大変な人にとって、玄関先まで食材が届くのは大きな助けになるからです。
ところが、時代は大きく変化しています。
実は、若者も「自炊したい気持ちはあるが時間や労力がない」「外食だけで栄養バランスを保つのは難しい」という悩みを多く抱えています。さらに「学業や仕事で忙しく、買い物の余裕がない」「料理のレパートリーを増やしたいけど何を買えばいいのかわからない」といった声も。
こうしたニーズに応えられれば、従来客層とは異なる新たな市場を獲得できる可能性が高まるのです。
また、若者層はSNSでの拡散力が強く、新しいものに積極的に触れたがる傾向があります。早い段階でサービスの魅力に気づいてもらえば、将来的に結婚やライフステージの変化があっても継続して利用してくれる可能性が高いでしょう。若いうちにサービスとの接点を持ってもらうことは、長期的なブランド価値の形成にも直結すると言えます。
固定観念の払拭がもたらす可能性
「食材宅配サービスは子育て世帯や高齢者が利用するもの」という固定観念は、若者のスムーズな加入を阻む大きな要因です。そうした先入観を変えるには、まず「若者でも気軽に始められる」「むしろ若い人こそ大きな恩恵がある」というメッセージを明確に打ち出す必要があります。
たとえば、仕事やアルバイトで忙しい大学生や新社会人なら、「時間を節約しつつ新鮮な食材を手に入れられる」「献立に悩まず済むキットを使えば、短時間で自炊を楽しめる」というメリットを訴求するのが効果的です。
そうすると「自分はまだ一人暮らしだから関係ない」という思い込みがガラリと変わる可能性があります。
さらに、固定観念を払拭するためには、オンライン広報だけでなくリアルな場での実証が必要です。実際に試食してみたり、注文方法に触れてみたりする体験があれば、「イメージとまったく違った」「思っていたより簡単だし、コスパも悪くないかも」と気づいてもらえるでしょう。
競合環境がもたらす差別化の必要性
食材宅配サービスが増加し、いくつもの類似ブランドがしのぎを削る状況では、「ほかとは違う魅力」を打ち出さなければ埋もれてしまいます。オンライン注文のUI/UX、配達の柔軟性、食材の鮮度や品質、レシピや栄養面のサポートなど、アピールポイントは多岐にわたることでしょう。
若者に向けては、とりわけ「時短性」と「楽しさ」を感じさせられるかがポイントになりやすいです。SNSでも写真映えする食材やミールキット、あるいは料理初心者でも失敗しにくいサポート体制など、「これなら自分でも続けられそう」と思わせる仕組みが求められます。
また、サステナビリティやエコへの配慮など、社会的に意識の高いユーザーを惹きつける要素も付加できるとなおよいでしょう。しかし、こうした差別化ポイントを単に文字や画像で並べても、若者にはその価値がなかなか伝わらないものです。
そこで、「一度実際に味わってみよう」「画面を触ってみよう」と興味を持ってもらうオフラインの仕掛けが必要なのです。
オンライン×オフライン活用の重要ポイント
若者の情報収集源はSNSやWeb検索が中心です。SNS広告やリスティング広告、インフルエンサーの口コミなどを駆使して認知度を高めることは大切です。
しかし、その先にある「実際に使ってみようか」「どうせなら体験してみたい」という気持ちをどう形にするかがポイントになります。
オンラインで興味喚起 → オフラインで納得 → オンラインで継続利用
この流れをファネルとして整備すれば、多くの潜在顧客が「なんとなく気になる」状態から「具体的に試してみたい」という段階へ進みます。オフラインの試食会やイベントでしっかり満足してもらえれば、そのままオンライン登録やアプリダウンロードへと誘導しやすくなるわけです。
若者ゆえにスマホ操作には慣れているケースが多いので、「イベントで得た好印象を、オンラインシステムで手軽に実行できる」という導線が完成すると、高い確率で新規会員登録につながります。
フェスやイベントでの試食会が効果的な理由
フェスや地域イベントなど、人が集まりやすい場所でのオフライン施策は、若者に「実際に味わう」「実演を見てシステムにふれる」体験をしてもらうための絶好のチャンスです。なかでも試食会は、食材宅配サービスならではの魅力をダイレクトに伝えられるため、大きなインパクトを与えられます。
若者が集まりやすいロケーションの選び方
フェスと言っても、その内容や来場者層はさまざまです。若者向け施策なら、以下のようなロケーションが狙い目です。
- 大学の学園祭:学生が多数来場するため、潜在顧客が多い。また、学業とバイトで忙しい若者に「時短+自炊」の価値を訴求しやすい。
- 音楽フェスやアートフェス:トレンドに敏感な若者が集まりやすく、新しいスタイルやサービスを積極的に受け入れる傾向が強い。
- 商業施設や駅前の大型イベント:休日や夕方の時間帯に若者がショッピングや待ち合わせで立ち寄るケースが多い会場は、幅広い層へのリーチが期待できる。
味わう体験とシステム体験の相乗効果
ただ試食を提供するだけでなく、「この料理は実は調理時間10分で作れます」「注文画面からワンクリックで食材が届きます」という情報をセットにすることが大切です。こうして味と手軽さの両方を実感してもらうことで、単なる「おいしいね」だけで終わらず、「こんなに簡単に作れるなら、ぜひやってみたい」という気持ちが盛り上がります。
その場でタブレット端末を設置し、会員登録画面や注文シミュレーションを体験できるようにすると、参加者は「意外とやること少ないんだな」「手間がかかると思ったけど全然平気」と納得し、登録のハードルが大幅に下がるでしょう。
実演・対話が信頼感を高めるカギ
インターネットを通じての宣伝は拡散力が高い一方、どうしても「本当なのか?」と疑いの目を向けられがちです。ところがフェスやイベントでの対面接客であれば、サービス担当者やスタッフが直接説明・実演するため、その透明性や誠実さが相手に伝わりやすいというメリットがあります。
若者はトレンド情報に敏感だからこそ「騙されたくない」「イメージと実態が違うのは困る」と思っている人が多いことも考慮しましょう。リアルの場でしっかり疑問や不安を解決できれば、競合他社よりも一歩抜きん出て「ここなら信頼できるかも」という印象を刻むことが可能です。
ターゲット別・ロケーション別の施策
大学生・専門学生を狙うフェスへの出展
大学生や専門学生を狙ったオフライン施策の具体例を見てみましょう。学園祭や新入生歓迎イベントなどは、ターゲット層を大きく取り込む大きなチャンスです。例えば以下のようなアプローチを行い、「大学生や専門学生にこそ使い勝手の良いサービス」というイメージづくりを目指しましょう。
テントブースや屋台形式でのメニュー提供
- 小腹を満たせる料理を用意し、「これは宅配食材を使って5分で作れます」という簡単な手順を提示してスピード感を強調する。
- 調理デモを入れても良いが、提供するメニューはすぐに食べられるような軽食・惣菜が望ましい。
学生証提示による特典設定
- 「学生証を提示すると割引価格で入会できる」「限定のサンプルセットをプレゼント」などの特別待遇を用意して、若者を歓迎する姿勢をアピールする。
- 「若者にこそ役立つサービスです」と明確に打ち出すことで、固定観念を払拭しやすくなる。
友達同士で楽しめる“時短クッキング”アクティビティ
- あらかじめセットされた材料を使い、5分以内で一品を完成させる「時短クッキング対決」や「味わい当てクイズ」を実施。
- できあがった料理を互いに試食しあうため、会話が自然に広がり、「こんなに便利ならみんなで始めようか」というポジティブな気持ちを共有しやすい。
- SNSへの投稿を促せば、仲間内やほかの学生への拡散効果が期待できる。
こうしたイベントを学園祭やサークル紹介など、大学生活の節目に合わせて定期的に行うと、サービスの認知が高まりやすいだけでなく、「新入生歓迎」の流れに乗って入会者を増やす好機にもなります。
都市部オフィス街での夕方試食ブース
都市部のオフィス街は、社会人にアプローチしやすいロケーションです。特に「退勤後の時間帯」を狙い、以下のような取り組みを行うとスムーズに新規会員獲得が期待できます。
開催時間と場所の選定
- 平日17:00〜20:00前後に開催すると、仕事帰りの社会人が立ち寄りやすい。
- オフィスビルのロビーや駅前広場など、人通りが多いスポットを選び、「帰宅途中に気軽に試食OK!」と案内できる看板やポップを設置する。
短時間調理のデモンストレーション
- 1〜2人暮らし向けのミールキットを、その場でサッと調理し、完成までの手軽さを直接見せる。
- 加熱を必要としないサラダや、手仕込み済みの惣菜も用意し、帰宅後すぐに食べられる利便性を強調する。
- ブース自体は小さめでもよいため、「これくらいのスペースで充分調理できます」と伝えることでハードルを下げる。
メリットの訴求とその場登録の仕組みづくり
- 「忙しい平日夜でも使いやすい」「週に1回届けてもらえれば、帰宅後に買い物をしなくて済む」など、具体的な購入メリットをパネルやスタッフ説明で提示する。
- その場で会員登録に進めるよう、スマホ登録用のQRコードやタブレットを用意し、「初回割引」「無料配達期間」など特典を案内する。
追加プロモーション策
- SNSフォトスポットを設置し、ハッシュタグ付き投稿でポイントやクーポンを付与するなど、オンライン拡散を狙う取り組みを盛り込む。
- 後日、来場者にイベント限定クーポンや新メニュー案内をメールやSNSで送信し、「試してみようかな」と思い出してもらう。
このようなブースによって「スーパーに寄る手間から解放される」「夜の時間を有効活用できる」というメリットを実感してもらえれば、若い社会人層の利用意欲を大きく高められます。
地域を巻き込むイベントとSNS活用
地域密着の催しやマルシェに出店するのも、若者へのアピールには有効です。環境意識や地産地消への関心が高い人も多く、以下のようなストーリーを伝えると興味を持ってもらいやすいでしょう。
地元生産者の顔が見えるブースづくり
- 地方の契約農家や漁港から取り寄せた食材を並べ、「この野菜は◯◯県の契約農家が朝採りしました」といった情報を添えつつ試食を提供する。
- 生産者の写真やこだわりの育成方法を示すメッセージパネルを掲示し、「収穫から翌日配達が可能」といった流通背景を視覚的に紹介する。
ゲーム感覚の調理体験や試食会
- 簡単なクッキング対決を用意し、参加者同士で「時短具合」「味付け」「盛り付け」を採点し合うなどのイベントを実施する。
- 体験後には「これなら家でもできそう」「地産食材でもレシピが豊富だね」といった声が自然に上がるため、そのまま帰宅後の利用イメージを持ってもらいやすい。
SNS発信と特典の連動
- 作った料理やイベントの様子を撮影・投稿することで「割引クーポン」がもらえる仕組みにすれば、拡散効果が狙える。
- イベント後に情報を共有できるよう、参加者のアカウントをフォローしておき、フォロワー限定の追加キャンペーンや地域限定メニューを告知する。
環境や地域への配慮を打ち出すことで、「持続可能な社会への貢献」「フードロス削減」の側面にも注目が集まり、興味を持った若者が自然とSNS拡散や口コミでサービスを広めてくれます。結果として、新規会員の獲得だけでなく長期的なファン形成にもつながるでしょう。
入会ハードルの低減策と具体的アプローチ
登録フローを簡単化するツールとサポート
若年層でも、面倒な手続きを嫌う人は少なくありません。特に「書類を細かく記入する」「クレジットカード情報や個人情報を何度も入力する」と聞くと、ためらうケースもあります。そこで、イベントブースにスマホ・タブレット登録を導入して、最小限の手順で申し込みができるよう配慮しましょう。
- イベント会場に専用QRコードを掲示し、その場でスマホから登録フォームを開いてもらう。
- 住所や支払い方法など、必要箇所だけを簡潔に入力できるUIを用意し、スタッフが横でサポート。
- 「登録完了で試食メニューをプレゼント」「SNSフォローで次回使える割引クーポン」といった即時特典を設定する。
これらの配慮をすると、実際に登録するための行動をしてもらいやすくなります。
お試し期間・特典プランの魅力づけ
初回にお得なお試しプランを打ち出すことで、若者が試してみようという気持ちを持ちやすくなります。たとえば「1週間分のミールキットが特別価格で体験できる」「初回配達料無料」など、リスクを感じさせない施策は効果絶大です。
加えて、短期間で「このサービスなら続けられそう」と納得してもらうために、専用のレシピ本や調理チュートリアル動画を提供してはいかがでしょうか。こうしたサポートコンテンツによって「調理に失敗しにくい」「毎日の献立を考えなくていい」という安心感が得られれば、継続率向上にもつながります。
価格面や費用対効果の伝え方
コスト比較と時短メリットの見える化
若者が食材宅配サービスを敬遠する理由の一つに「割高では?」という懸念があります。ところが、実際にはコンビニ食や外食、デリバリーを繰り返していると、トータルコストは割高になりがち。加えて、スーパーまでの交通費や時間を考慮すると、宅配のほうがメリットが大きい場合もあります。
そこで、以下のような指標を提示すると分かりやすいでしょう。
- 1カ月あたりの外食やデリバリー時の平均費用と、宅配サービス利用時の費用差
- 買い物時間や交通費を削減できることでの“時給換算”のメリット
- 捨ててしまう食材削減や、余計な買い物を防げることによる節約効果
イベント会場で実感させるプレゼン手法
フェスや試食会の場で、実際に「毎日の買い物の手間がどのくらい省けるか」「食材廃棄をどの程度減らせるか」を視覚化したパネルやスライドを使って説明しましょう。特に「1週間分の買い物で◯円得する」「大学付近の外食単価と比較すると◯円の差」など、具体的な数字を示すと説得力が高まります。
若者は合理性を重視する一方で、楽しさや直感も大切にする層です。数値データだけでなく、「カラフルなイラスト」「わかりやすい動画」などを組み合わせたプレゼンを行い、専門用語を多用せずにメリットを伝えると、より強い興味を引き出せるでしょう。
ロイヤルティの向上と離脱防止の具体策
オフライン接点の継続活用
一度登録してもらえたら終わりではなく、継続的な利用へとつなげるための仕掛けが必要です。若者はライフスタイルや気分の変化が激しいため、定着する前に離脱してしまうリスクがあります。
そこで、イベントやフェスへの定期的な再出展、あるいは店舗型ポップアップの開催を続けるのも一手です。「会員限定の新メニュー試食会」「SNSフォロワー限定のリアルイベント招待」など、再度足を運ぶ理由を設けることで、「最近ちょっと注文頻度が減ってきた…」というユーザーとも接点を持ち、利用を再活性化させやすくなります。
会員コミュニティ形成で生まれる相乗効果
若者が長くサービスを利用するためには、コミュニティ感や仲間意識を高める施策が有効です。SNSでのグループや投稿企画を通じて、ユーザー同士がレシピや活用アイデアを共有できる仕組みを整えると、「自分だけでなくみんなが使っているから続けやすい」「話題や情報交換が楽しい」と思ってもらえるようになります。
また、コミュニティ内で人気の高い食材やミールキットをランキング形式で紹介すると、他のユーザーが新たな商品を試すきっかけにもなります。こうした相乗効果が、離脱防止や追加購入を促す原動力となるでしょう。
まとめ:若者の“リアルな体験”こそが最大の突破口
食材宅配サービスが「子育て世代や高齢者だけのもの」という固定概念を崩し、若者から爆発的な人気を獲得するためには、オンラインとオフライン両面でのプロモーションが不可欠です。
特にフェスなどのオフラインイベントで試食体験やシステム体験を提供すれば、味や使い勝手の良さを五感で感じてもらえます。「実際にやってみたらイメージと違って簡単だった」「思ったより味もいいし、コスト的にも悪くない」といったポジティブな反応につなげやすいでしょう。
さらに、イベントの場で会員登録まで完結できる仕組みを整え、SNSやお試しセットで後押しすれば、実際の利用にスムーズにつなげやすくなります。加えて、その後のコミュニティ形成や定期的なオフライン施策により、ロイヤルティを高め、離脱を防止することも可能です。
何より、若者は「リアルに体感すること」を重視する傾向があります。競合サービスとの差をハッキリと体感させられれば、「一度使ってみたい」というモチベーションが大きく高まりやすいはずです。オンラインだけでは伝わりにくい魅力があるからこそ、対面接客やイベント実演を取り入れながら、新規会員獲得へと結びつける。こうした戦略を粘り強く継続していくことで、従来にはなかった若いファン層を拡大する大きなチャンスが巡ってくるのではないでしょうか。
執筆者:株式会社セレブリックス MX事業本部 マーケティングビジネスデザイン室 石田真理子