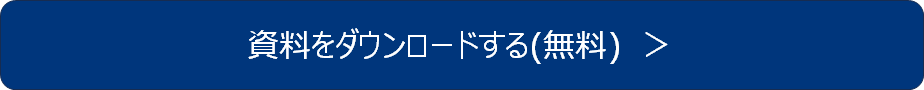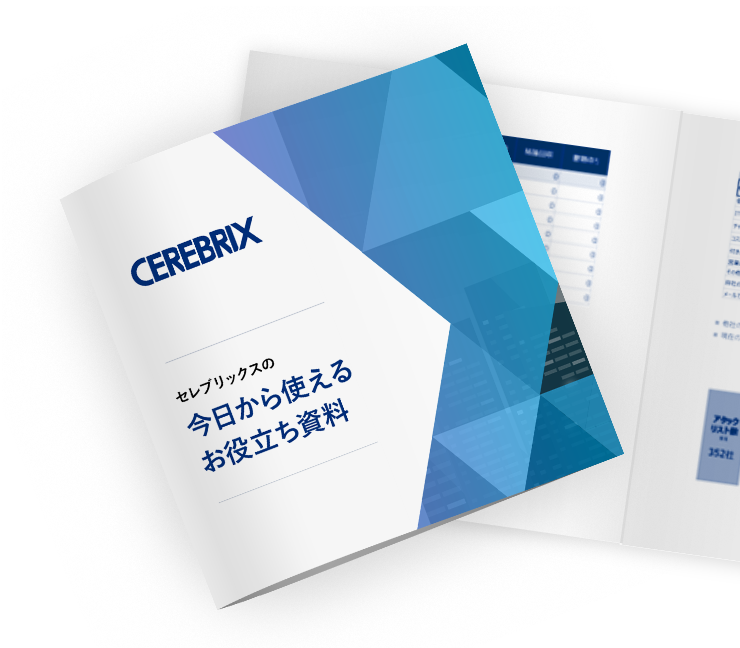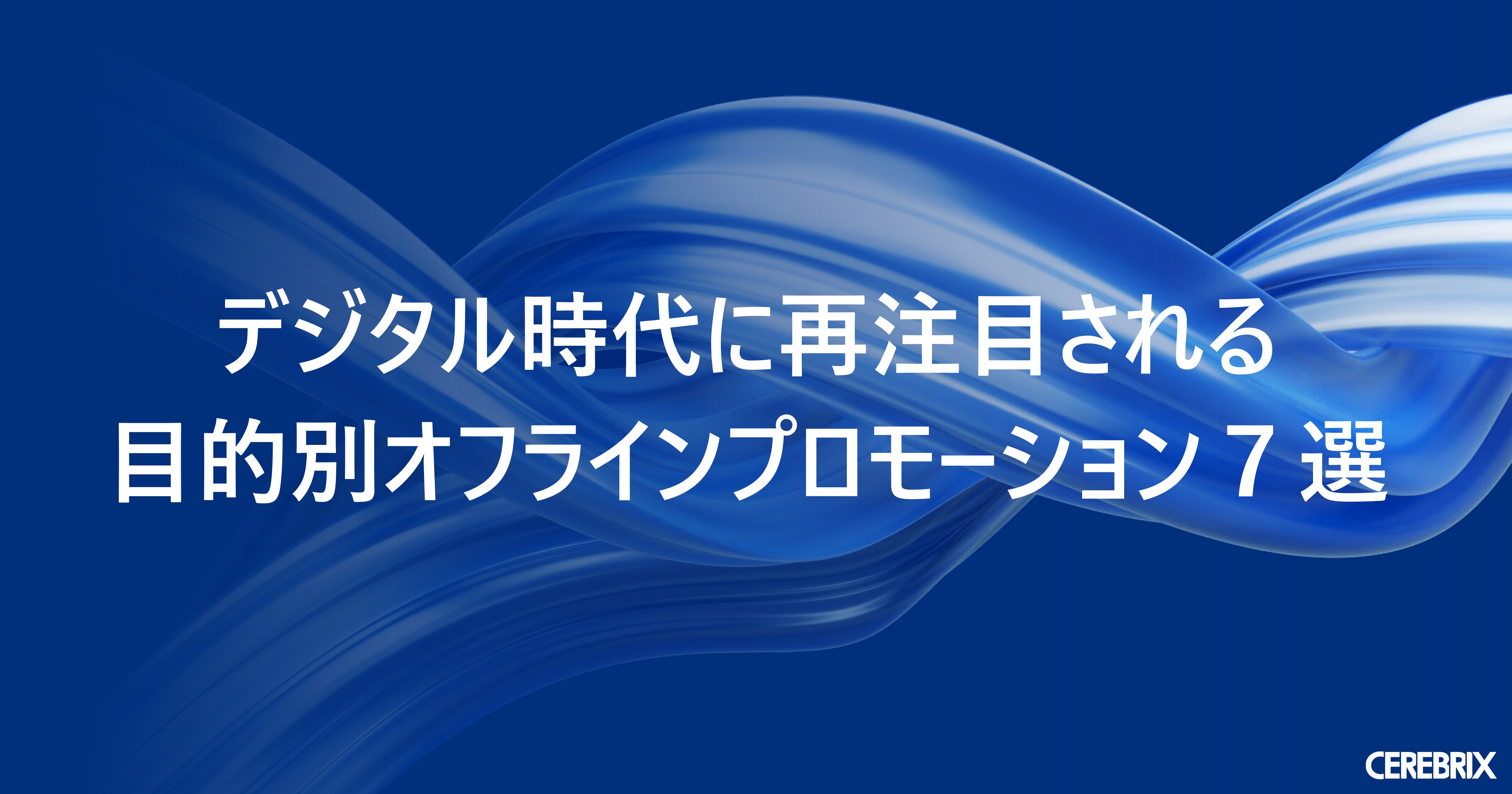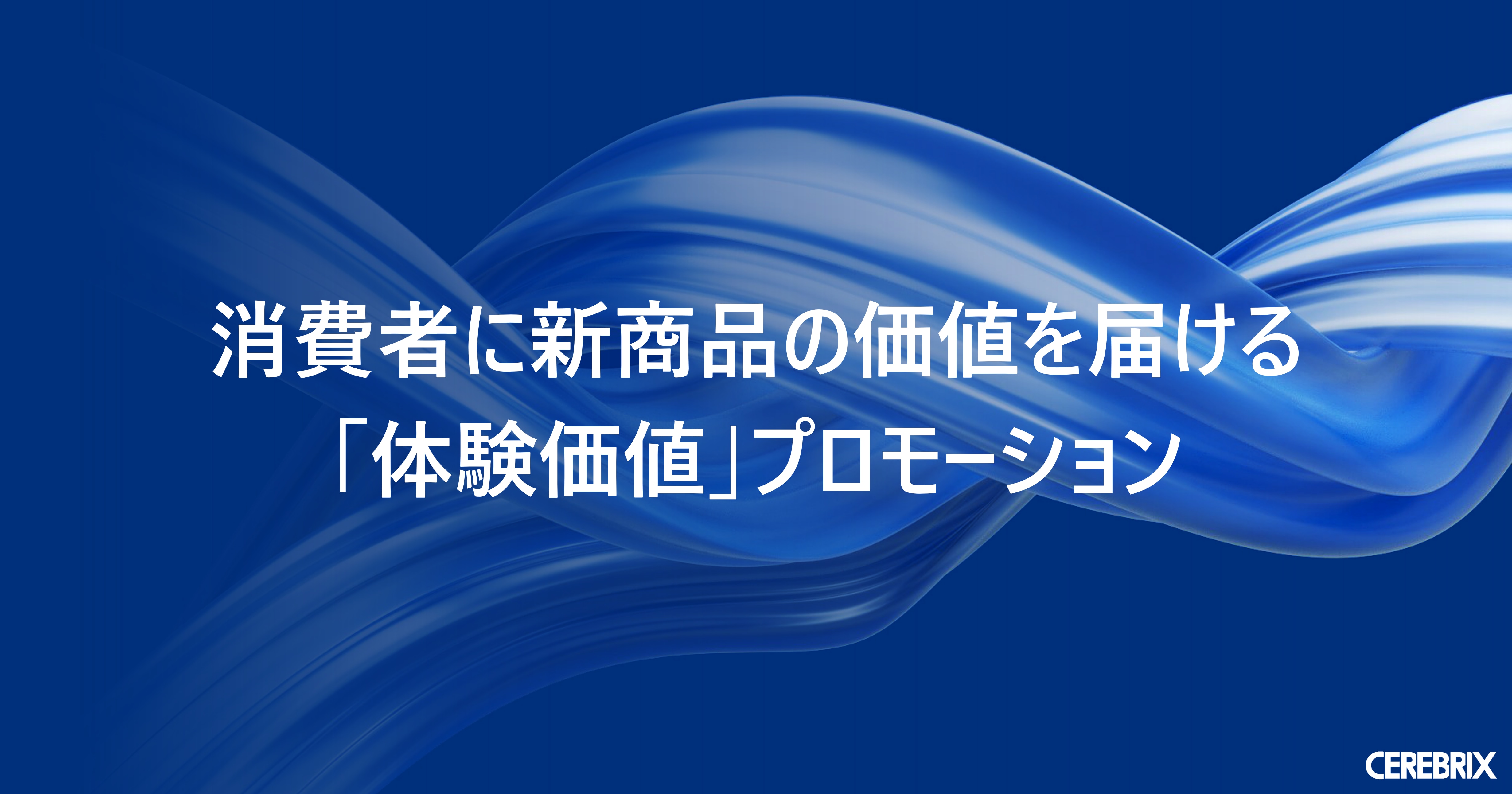デジタル時代にこそ選ばれる再注目のプロモーション手法とは?
皆さんが直近で採用するマーケティング手法はデジタル施策一辺倒になっていませんか?
昨今、あらゆる環境においてデジタル化が進み、マーケティング手法においてもオンライン広告、動画広告、SNS広告、SNS運用とマーケティング手法の主流はデジタルに移行してきました。
デジタル施策はある種の飽和状態に入っていて、企業のマーケティング担当者も口を揃えて
「効果は一定出ているが、これ以上伸ばす方法がよくわからない」
といったお声をよく聞きます。
このような背景があるからこそ、人を介したマーケティング施策である”オフラインプロモーション”に目を向けてみるのはいかがでしょうか。現在、消費者に直接対面でコミュニケーションを図り、「顧客体験」を通して態度変容をさせる、リアルなプロモーション手法が再注目され始めています。
本記事では、そんなオフラインプロモーションを得意とする「セレブリックス」の事業内容を詳しくご紹介し、なぜこの時代にオフラインの施策が必要なのか、その魅力を深掘りしていきます。
あわせてお読みください
本記事とあわせて、『デジタル時代に再注目される目的別オフラインプロモーション7選 』もぜひご活用ください。デジタルだけでは得られない【人を介したリアルな顧客体験】を提供するオフラインプロモーションの魅力に再注目。対面でコミュニケーションを図ることで、顧客の態度変容を促す手法をご紹介しています。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、オフラインプロモーションが必要なのか
- 2.オフラインにこだわるメリットとは
- 3.オフラインプロモーションの種類
- 3.1.店頭・商業施設でのプロモーション
- 3.2.街頭・屋外でのプロモーション
- 3.3.イベント・エンターテインメント施策
- 3.4.体験型・エクスペリエンシャルマーケティング
- 3.5.セールス・ダイレクトマーケティング系
- 3.6.PR・メディアリレーションズ系
- 3.7.その他のリアルプロモーション手法
- 4.オフラインプロモーション支援を依頼するならセレブリックス
- 4.1.セレブリックスのオフラインプロモーションが選ばれる理由5選
- 4.1.1.データ収集・分析へのこだわり
- 4.1.2.プロモーションキャストの質と育成
- 4.1.3.豊富なソリューションをワンストップで提供
- 4.1.4.博報堂グループとの連携による総合力
- 4.1.5.高速PDCAで成果を伴走支援
- 5.セレブリックスの支援事例
- 6.まとめ:これからのマーケティングはオフラインとデジタルの二刀流がカギ
なぜ今、オフラインプロモーションが必要なのか
近年、企業のオンラインマーケティング戦略は急速に台頭し、とりわけコロナ禍を契機に加速してきました。しかしその結果、競争の激化により広告費用対効果が伸び悩むケースが増えています。こうした”デジタル施策の飽和状態”だからこそ、人を介して対面で行う「オフラインプロモーション」が現在再び注目されています。
対面ならではの深いコミュニケーションを行うオフラインプロモーションは、その場で疑問や不安を解消できるため満足度が高まり、ブランドへの好感度も上がりやすい点が大きなメリットです。デジタルに飽和感が漂う今こそ、さらにオフライン(対面)を組み合わせた二刀流戦略で得られる相乗効果を最大限に活かすべきではないでしょうか。
オフラインにこだわるメリットとは
オフラインプロモーションのメリットは「実際の体験を通じて顧客の印象を強固にする」点にあります。オンラインで目にする情報のみでは伝わりにくかった質感や味、においなどをダイレクトに体感できることで、商品への高評価やブランドロイヤルティにつながるのです。さらに、イベント会場や店舗での直接対応は、消費者の声をダイレクトに拾い上げられるため、商品改善や新サービスの企画にも生かしやすい強みがあります。
オフラインプロモーションの種類
そんなリアルプロモーションには、具体的にどのような手法が存在するのでしょうか。
具体例を網羅的に挙げていきます。
店頭・商業施設でのプロモーション
- 店頭デモンストレーション試食/試飲会
例:新商品の化粧品を販売員が実際に試しながら接客する、食品をその場で調理し試食してもらう 等 店舗内サンプリング/クーポン配布
例:新商品のサンプルを来店客に直接手渡す、レジや販売カウンターでクーポンを配る 等- POP&ディスプレイ訴求
対面接客とも連動しやすく、商品陳列に工夫を凝らすことで販売員がその場で説明・誘導する 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 新商品やサービスの使用感をその場で体感してもらいたい場合
- 商業施設などで自然な集客が見込める環境で直接訴求したい場合
- 試食やデモで購買意欲を高め、即時の売上アップを狙いたい場合
■この手法を採用するメリット
- 対面コミュニケーションにより、商品の魅力を瞬時に伝えられ購買につなげやすい
- 目の前で体験することで、信頼感と興味を高め、ブランドロイヤルティを醸成できる
- POPやディスプレイの装飾を組み合わせることで、視覚的なインパクトと説明の説得力を強化できる
- クーポン配布や試食後のフィードバック収集が容易で、その場で改善や追加施策を検討しやすい
街頭・屋外でのプロモーション
- 街頭サンプリング・ビラ配り
例:駅前や商業施設周辺でサンプリングスタッフが新商品の試供品や案内チラシを配布する 等 - 街頭イベント・ゲリラプロモーション
例:特定の場所でフラッシュモブやパフォーマンスを通じてSNS拡散を狙う(デジタル拡散は含むが、実施は対面) 等 - 移動型プロモーション(ロードショー/移動販売車)
例:移動販売車で試食と合わせてブランドや商品の訴求を行う、全国主要都市を回るロードショー 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 多くの通行人が集まる駅前や繁華街などで、一度に大量の潜在顧客へリーチしたい場合
- 話題性やイベント性を重視し、SNSなどを活用して拡散を狙いたい場合
- 地域ごとにターゲットの特性が異なるため、移動しながら最適な場所でPRしたい場合
■この手法を採用するメリット
- 直接手渡しや対話によってブランドや商品への印象を強く残せる
- ゲリラ的な施策や移動販売車で注目度を高め、大きな話題づくりにつなげやすい
- 短期集中で成果が出やすく、費用対効果を確認しながら柔軟に展開を変えられる
- ロードショー形式なら、全国規模での認知拡大やエリアごとの新規獲得が期待できる
イベント・エンターテインメント施策
- 展示会・見本市・トレードショー出展
例:業界向けイベントで製品ブースを設け、実際に担当者が対面でプレゼンを行う 等 - カンファレンス・セミナー・ワークショップ
例:主催または協賛として開催し、講師やスタッフが直接参加者と触れ合いながら情報提供や体験を促す 等 - ポップアップストア/期間限定ショップ
例:新ブランドや新商品を期間限定で展開し、ブランド体験を深めてもらう 等 - スポンサーシップ・協賛イベント(スポーツ、音楽フェスなど)
例:スポーツ大会や音楽フェスのスポンサーとしてブースを出店し、スタッフが製品紹介や体験会を実施する 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 業界特化型イベントや見本市に参加し、新規リードや取引先を開拓したい場合
- セミナーやワークショップを通じて集客力を高めながら、自社サービスへの理解度を深めたい場合
- ポップアップストアなどの期間限定施策で、商品・ブランドの世界観を体験してもらいたい場合
- スポーツや音楽のイベントを活用し、幅広い層へ自然にアプローチしたい場合
■この手法を採用するメリット
- イベント自体の集客効果が高く、ターゲットに直接リーチしやすい
- 参加者が興味を持った状態で来場するため、商品・サービスのプレゼンや体験がスムーズに進む
- ブランドの世界観を演出しやすく、他社との差別化を明確に打ち出せる
- スポンサーシップや協賛を通じて、ブランドイメージや知名度の向上が期待できる
体験型・エクスペリエンシャルマーケティング
- 体験会・ワークショップ・レッスン
例:商品の使い方指導や実演クラスを開き、実際に触って使ってもらうことで理解・購買意欲を高める 等 - リアル脱出ゲームやARイベントと組み合わせた体験企画
例:会場にプロモーションブースを設置し、ゲーム内で商品やサービスを絡めた体験を提供する 等 - ブランドアンバサダーやスタッフとの直接対話
例:ブランドスタッフが商品やブランドコンセプトを丁寧に説明しながら、来場者と深いコミュニケーションを行う 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 商品やサービスの特徴を五感で体感させ、深い理解と興味を引き出したい場合
- ゲームやイベント要素を加えることで、楽しみながらブランドに触れてもらいたい場合
- ブランドアンバサダーを活用して、ファンコミュニティを形成し継続的な支持を得たい場合
■この手法を採用するメリット
- 参加者が実際に体験するため、印象に残りやすく購買意欲が高まりやすい
- 没入感のあるコンテンツがSNSなどの話題になりやすく、口コミ効果が期待できる
- スタッフやアンバサダーとの対話がブランドへの信頼度アップにつながり、長期的な関係を築きやすい
- エンターテインメント性が高いので、顧客満足度を高めながら販促活動を行える
セールス・ダイレクトマーケティング系
- 訪問販売・対面セールス(BtoC/BtoB)
例:営業担当者が企業や一般家庭を訪問して直接コミュニケーションを図り、商品やサービスを案内する 等 - 店舗やショールームでの個別相談会・相談カウンター
例:保険会社や通信会社が店舗でスタッフが常駐する相談カウンターを設け、対面で商品説明・契約手続を行う 等 - テレマーケティング(電話を介するがデジタルではなく人の対話に重きをおく)
直接顔を合わせるわけではないが、人による対話を主体としたマーケティングとして活用される場合がある
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 高額商品や複雑なサービス内容など、対面や会話で丁寧に説明/フォローする必要がある場合
- 潜在顧客の課題をしっかりヒアリングしながら、適切な提案を行いたい場合
- 契約や購入の意思決定までのステップを対話でサポートし、クロージング率を高めたい場合
■この手法を採用するメリット
- 顧客の悩みに直接応えながら、深い信頼関係を構築できる
- 商品やサービスの詳細・メリットを対話形式で伝えられるため、納得度が高い
- 対面・電話いずれも顧客の声をリアルタイムに拾えて、その場で柔軟な対応が可能
- フォローアップを重ねやすく、リピートやアップセルにもつなげやすい
PR・メディアリレーションズ系
- 記者会見・メディア向けイベント
例:新商品発表会を催し、参加した記者やメディア関係者に対して直接プレゼンテーションを行う 等 - 試写会・試乗会・発表会
例:新車の試乗会や映画の試写会を開催し、招待されたメディア・一般参加者に直接プロモーションする 等 - インフルエンサーを招いたリアルイベント
例:有力ブロガーや著名人を会場に招き、ファンと直接交流させることでブランド体験を広げる 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 多くのメディアやインフルエンサーに商品の魅力を直接伝え、一気に拡散したい場合
- 新商品リリースなど大きなアナウンスを、記者会見やイベント形式で印象的に発表したい場合
- 会場で試乗や試食などの実演を行うことで、より具体的なレビューや反響を得たい場合
■この手法を採用するメリット
- メディアを通じた広範囲の露出が期待でき、認知度向上に大きく貢献する
- 直接参加した記者やインフルエンサーが体験レポートを発信するため、信頼性が高い情報として拡散されやすい
- 試写会や試乗会など体験要素があると、ポジティブな口コミやSNS投稿を誘発しやすい
- ブランドの世界観をイベント全体で演出でき、顧客やメディアに一貫したイメージを訴求しやすい
その他のリアルプロモーション手法
- ノベルティ・サンキューギフトの手渡し配布
例:展示会や店頭イベントで、記念品や小物をスタッフが直接手渡しすることで、認知拡大や好感度向上を図る 等 - アンケート・調査会(街頭や店内での対面ヒアリング)
例:調査員が街頭で商品認知度や満足度を直接ヒアリングし、回答者に試供品を渡す 等 - コミュニティマーケティング(リアルコミュニティの形成)
例:ファンクラブや地域コミュニティを作り、直接コミュニケーションしながら商品の訴求やイベントを開催する 等 - ロードマップツアー・企業施設見学会
例:自社工場やショールームを見学してもらい、スタッフが直接案内や解説をする 等
■どんなシーンでこの手法を採用すべきか
- 顧客やファンに直接感謝を伝えたり、絆を深めたい場合
- 商品の満足度や認知度を、リアルな場でヒアリングして改善アイデアを得たい場合
- コミュニティを形成し、長期的なファンづくりやリピート購入を促進したい場合
- 実際の製造現場やサービス提供現場を見せることで、信頼度や興味を高めたい場合
■この手法を採用するメリット
- 手渡しでのノベルティ配布は、心理的にもブランドへの好感度が高まりやすい
- 対面のアンケート調査は、より本音に近い回答を得られるため、商品開発やプロモーション改善に役立つ
- コミュニティマーケティングにより、ファン同士の交流や口コミが自然に広がり、ブランドロイヤルティを強化できる
- 企業施設見学などで裏側を見せることで、透明性や信頼度が増し、長期的な顧客の獲得や定着につながる
オフラインプロモーション支援を依頼するならセレブリックス
数多く存在するプロモーション会社の中でも、セレブリックスは“人を介したセールス力”を武器にしたマーケティングパートナーです。サブスクやアプリなどのBtoC商材に向けた新規顧客獲得から、全国規模のサンプリングや推奨販売・デモンストレーション販売、会員獲得・入会促進活動までをトータルに支援しています。DMやテレアポなどのオンライン施策に加え、実店舗やイベント会場での対面販売、訪問販売といったオフライン施策も組み合わせ、全国の優秀な販売員派遣からスタッフ教育、ロケーション選定、物流管理、効果測定までワンストップでカバーできます。さらに、QRコードや独自ツールを駆使してリアル施策でもデータを正確に取得・分析し、オンラインと連動させるOMO戦略を強化しています。その結果、「ただのサンプリング屋さん」にとどまらず、“リアルだからこそ得られる生の情報”をしっかり活用した成果重視の顧客獲得と売上アップを実現しています。
セレブリックスのオフラインプロモーションが選ばれる理由5選
データ収集・分析へのこだわり
- 実際に対面するオフラインの接点から得られる顧客の声や反応をデジタルツールで可視化し、その場しのぎではない継続的な改善が可能。
- 「オフラインプロモーションはデータを取りにくい」という課題を、独自の仕組みと分析体制でしっかりカバー。
プロモーションキャストの質と育成
- 日本全国の、現場対応力とホスピタリティを兼ね備えた“現場力”を提供。
- 商品理解やターゲット分析の研修を徹底することで、高い接客クオリティを維持。
豊富なソリューションをワンストップで提供
- オンライン施策(DM、テレアポなど)からオフライン(店頭販売、イベント、訪問販売など)まで、あらゆる販路を一気通貫で提案。
- スタッフ手配や物流、効果測定まで含めたトータルサポートで、担当者の負担を軽減しつつスピーディーな展開が可能。
博報堂グループとの連携による総合力
- グループ会社である博報堂とのネットワークを活かし、プロモーション段階だけでなく、より上流の戦略立案から広告クリエイティブ面まで柔軟にサポート。
- グループシナジーにより、大規模企画や全国展開にも強く、幅広いマーケティング施策を実現。
高速PDCAで成果を伴走支援
- 1,300社・12,600商材以上の支援実績で培ったノウハウをベースに、現場の状況を即時にフィードバックし、施策を改善。
- 単なる「人材派遣」で終わるのではなく、顧客獲得や売上アップといった成果を重視する運用体制を整備。
セレブリックスの支援事例
英語学習へのハードルを「楽しい体験」で下げる
ある大手キャラクター関連企業が提供する幼児向け英語教材の新規顧客獲得において、0歳~3歳のお子様をお持ちの親御さんとそのお子様に向けて「楽しい体験の提供」にこだわった支援を実施。
「英語教材なんてうちの子にはまだ早いのでは?」とお考えの親御さんも多くいらっしゃる中で、セレブリックスがこだわったのは"直接対面するからこそ提供できる体験”の創出でした。
「売る」ということではなく、利用するお子さん本人がこの英語教材に触れて「楽しい!と感じる」ことを重視。親御さんの信頼を得ることはもちろんのこと、お子さんが営業パーソン自身を好きになり、笑顔になれるようなコミュニケーションに重きを置いています。「営業自らもお子さんと一緒になって教材を楽しむ」ことで、オフライン(対面)でしか味わうことのできない、楽しい体験を提供するのがこだわりです。
実際、体験で盛り上がるお子さまの様子を見た親御さんの中には、実際に触ってみると、お子さんが高い興味を示すことを実感しその場で購入を決意される方もいました。親御さんがWebサイトで閲覧するだけではなく、お子さんが実際に気に入るかどうかが最も重要であり、その反応を見られるのが体験提供型の営業の大きなメリットです。
楽しい体験×専門知識が生む、オフライン営業の可能性
ただ楽しい体験を提供するだけではありません。セレブリックスの営業パーソンは商材ごとの専門的な知識のインプットにも率先して取り組んでいます。
例えば先の例で言うと、英語の習得にあたって、将来発音が美しく行えるようになるかどうかは英語と日本語の発音の数の違いが聞き分けられるようになる0~3歳時期に決まると言われています。
そのため学習にもっとも適切な時期が乳幼児期なのです。このような、扱う商材における比較的専門性の高い知識のインプットも欠かせません。週ごとのミーティングでこれらの知識や提案時のトーク例を営業パーソン内で共有し合い、商品の特長や英語学習の必要性を適切に伝えられるようブラッシュアップし続けているのがポイントです。
このように、「顧客の印象に残る体験の提供」と、過去1,300社・12,600商材を超えるさまざまな商材の営業販売経験から得られた「商材の属性ごとの販売ノウハウ」を活かし、対面という直接の接点で高い成果と満足度を生み出すのがセレブリックスの強みです。もし「自社商品をより広く届けたい」それも、「リアルなオフラインの場で確かな手応えを得たい」というお考えがあれば、ぜひセレブリックスのオフラインプロモーションをご検討ください。
まとめ:これからのマーケティングはオフラインとデジタルの二刀流がカギ
これからのマーケティングはオフラインとデジタルの二刀流がカギです。デジタル一辺倒の打ち手だけでは、ユーザーの興味関心を引きつけるのが難しくなってきています。一般的なカスタマージャーニーマップを紐解いてみると、「認知・興味関心・情報収集」まではSNSやWeb広告などデジタル施策で効率的に接点を作り出す一方、「比較検討」や「購入」のフェーズでは、実際に対面するリアル施策が強力な決め手になります。
なぜなら、顧客が最後の一押しで抱える細かな疑問や不安は、人の顔が見える場でこそ解消されやすく、納得感のある“購入体験”を提供できるからです。今後は、リアル施策とデジタル施策をバランス良く活用し、一貫性ある情報提供と対面でのコミュニケーションを補完的に組み合わせたプロモーション施策が主流となっていくでしょう。
執筆者:株式会社セレブリックス MX事業本部 マーケティングビジネスデザイン室 石田真理子